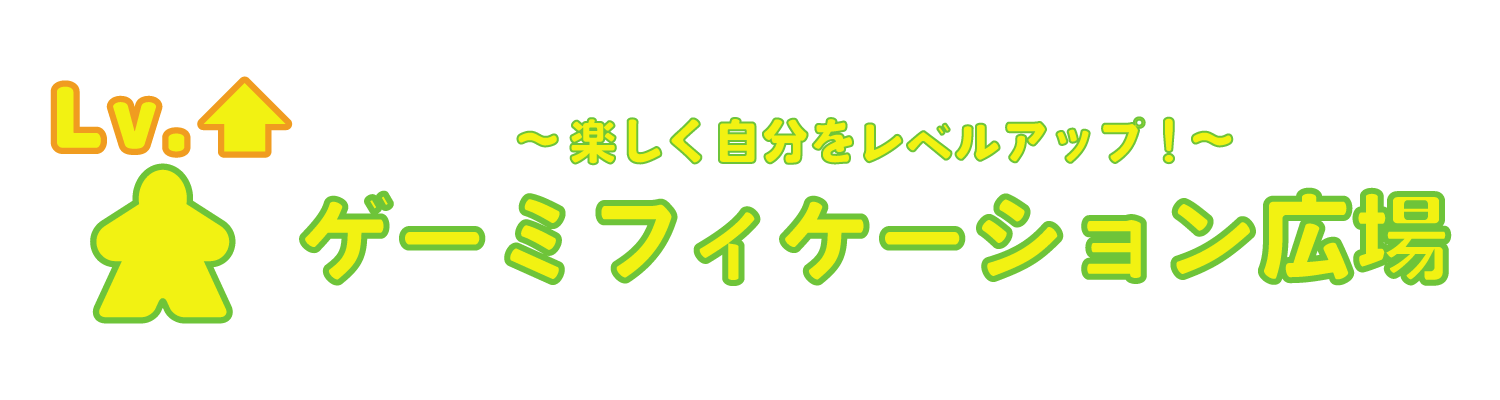- ブレーンストーミング(ブレスト)について知りたいTCGプレイヤー
- 新カードを使った強いデッキをいち早く作りたい
当記事では、TCGを例に用いて『ブレーンストーミング(ブレスト)』と『KJ法』について解説していきます。
当記事を読むことで、『ブレーンストーミング(ブレスト)』と『KJ法』について理解できる他、新カードを使った強いデッキをより早く構築できるようにもなるでしょう。
ブレーンストーミングとは?
ブレーンストーミング(以下ブレスト)とは、アレックス・F・オズボーン氏によって考案された
- 批判や否定をしない
- 自由にアイデアを出す
- 質より量を重視する
- アイデアを結合・発展させる
の4つを原則とした、あるテーマについての新たな発想や質の高い案を出やすくするための方法です。
TCGに例えると、新カードの情報が発表された時に、仲間との話し合いやSNSなどで各人が挙げた相性の良いカードをひたすらリストアップしていく感じです。
批判や否定をしない
批判や否定をしないことで、固定観念にとらわれないユニークなアイデアを出しやすくします。
TCGで例えると、『独特な効果を持つ新カード』を弱いと決めつけないといった感じです。
実際のTCGでも『独特な効果を持つ新カード』が、発売前の低評価を覆して環境トップになった事例が数多くあるので、固定観念にとらわれずに考えることが大事です。
自由にアイデアを出す
実現性度外視だったり、一見実用性皆無なアイデアでも活かせる可能性があるので、とりあえずでも出していきます。
TCGで例えると、「『A』と『B』はどちらも場に出すのが難しいが、揃ったらほぼ勝てる」程度でも1アイデアとして出す感じです。
実際のTCGでもネタデッキから環境デッキになった事例が数多くあるので、粗削りなアイデアでもとりあえず出していくことが大事です。
質より量を重視する
様々な角度から、多くのアイデアが出されることで、新たなアイデアが思いつきやすくなります。
TCGに例えると、同じカードでもアグロメインの人とコントロールメインの人では、相性が良いと挙げるカードが違う場合があるといった感じです。
アイデアを結合・発展させる
2つ以上のアイデアを組み合わせたり、アイデアの一部を変えてみることで、新たなアイデアを出していきます。
TCGで例えると、新カードと相性が良いカードとして挙がったカードと相性が良いカードを挙げてみたり、新カードと相性が良いカードとして挙がったカード同士のシナジーに注目したりする感じです。
ブレストの後は情報整理
ブレストは、とにかくアイデアの量を重視するので、どうしてもアイデアの数が多くなります。
そのため、リストアップしたカードからデッキとして成り立つようカードを選んでいくのと同じように、出たアイデアから良いアイデアを選んでいくことが必要です。
そこで、TCGと同じようにカードでアイデアを整理できる『KJ法』という方法を紹介します。
KJ法とは?
KJ法とは、東京工業大学名誉教授の川喜田次郎氏が考案したデータをまとめるための方法で
- カードの作成(付箋などにアイデアを1つずつ書く)
- グループ編成(似通ったものをグループ化する)
- 図解化(図にしてまとめる)
- 叙述化(文章にしてまとめる)
の4ステップで構成されます。
この4ステップは、TCGでデッキを構築する時の
- 採用候補カードを集める
- 似通った役割のカードをまとめる
- 枚数を調節してデッキにする
- デッキリストを書いたりデッキを言葉で解説する
という流れと似ているため、TCGプレイヤーは比較的実践しやすい方法なのではないでしょうか。
まとめ
ブレーンストーミングとKJ法を駆使することにより、アイデア出しや情報整理がスムーズになります。
アイデア出しや情報整理がスムーズになることで、いち早く課題を解決していけるようになるでしょう。