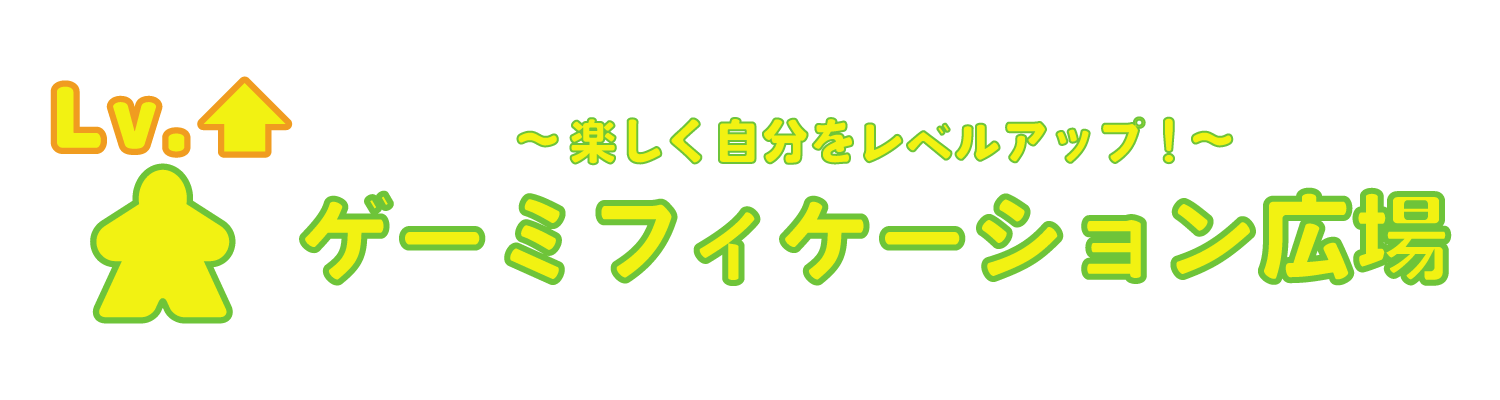- TCGが上手くなりたい
- リスク管理について学びたいTCGプレイヤー
当記事では、リスク管理について、TCGを例に用いて解説していきます。
当記事を読むことで、リスク管理について分かり、TCGも上手くなるでしょう。
リスク管理は『リスクとリターンの把握』『リスクヘッジ』が重要
リスク管理は『リスクとリターンの把握』『リスクヘッジ』が重要です。
ここからは『リスクとリターンの把握』『リスクヘッジ』について、TCGを例に用いて解説していきます。
リスクとリターンの把握
TCGでは、リスクとリターンを把握し、できる限りローリスクハイリターンな行動を選択することが重要です。
例えば、以下のような場面があったとします。
自分
支払えるコスト 8
手札 カードAが1枚、カードBが2枚
カードAの効果「コスト8 自分は、場の相手のカードを3枚まで選び、持ち主の手札に戻す。」
カードBの効果「コスト4 自分は、場の相手のカードを1枚選び、持ち主の手札に戻す。」
相手
場のカード 3枚(使われたカードと同じコストのカードを手札から1枚捨てることで効果を無効にするカードあり)
手札 1枚(内容不明)
上記の場面で、できるだけ多くかつ最低1枚は場の相手のカードを除去したい場合、以下の2つ選択肢があります。
| 選択肢 | 手札消費 | 支払うコスト | 除去できる数 |
|---|---|---|---|
| 1.カードAを1枚使う | 1 | 8 | 0~3 |
| 2.カードBを2枚使う | 2 | 8 | 1~2 |
1.は2.と比べて除去できる数が多く手札消費も少ないものの、効果を無効にされてしまった場合は、1枚も除去できません。
つまり、ハイリスクハイリターンといえます。
一方2.は1.と比べて除去できる数が少なく手札消費も多いものの、最低1枚は除去できるため、ローリスクローリターンといえます。
よって、上記の場面でできるだけ多くかつ最低1枚は場の相手のカードを除去したい場合は、最低1枚は除去できる2.が無難な選択といえるでしょう。
ハイリスクハイリターンの行動を選択する必要がある時もある
できる限りローリスクハイリターンな行動を選択することが重要なTCGですが、ハイリスクハイリターンの行動を選択する必要がある時もあります。
それは、ハイリスクハイリターンの行動を選択しなかった場合、試合に負けてしまう時です。
なぜなら、試合に負ける=最大のリスクだからです。
例えば、先ほどの場面で場にある相手のカード3枚全てを除去しなければ試合に負けてしまう場合は、効果を無効にされてしまう可能性はあるものの3枚全てを除去できる1.を選択する必要があります。
このように、状況によって最適な選択は異なるので、リスクとリターンの把握が重要という訳です。
リスクヘッジ
リスクヘッジとは、リスクを回避したり、リスクに対処できるようにすることを表す言葉です。
TCGでは
- 詰み防止用のカードをデッキに入れる
- 不利対面が少ないデッキを使う
- 環境デッキの対策をしたデッキを使う
- 自分のデッキの対策に使われるカードの対策をする
- よく使われるカードの対策をする
などがあたります。
適切なリスクヘッジをするには?
適切なリスクヘッジをするには、リスクヘッジをした際のリスクとリターンの把握が必要です。
例えば、カードCの対策にカードDをデッキに入れることを検討するとします。
カードDをデッキに入れると、カードCを使用したデッキへの勝率が上がります。
つまり、カードCの使用率が高いほどリターンが大きくなります。
しかし、カードDにデッキの枠を使うことにより安定性が下がるなどして、カードCを使用しないデッキへの勝率が下がってしまうというリスクもあります。
そのため、カードDをデッキに入れるのは、カードDをデッキに入れた方が全体的な勝率が高くなる(リスクよりリターンが大きい)環境の時にするのが良いといえるでしょう。
このように。リスクヘッジをする際には、リスクとリターンが見合っているかを見極めていく必要があります。
リスクとリターンが見合っているかを見極める方法については、以下の記事が参考になりますので、ぜひご覧ください。
まとめ
- リスク管理は『リスクとリターンの把握』『リスクヘッジ』が重要
- できる限りローリスクハイリターンな行動を選択することが重要
- ハイリスクハイリターンの行動を選択する必要がある時もある
- 状況によって最適な選択は異なる
- リスクヘッジをする際には、リスクとリターンが見合っているかを見極めていく必要がある
リスクとリターンを把握し、適切なリスクヘッジをすることで、より良い選択がしやすくなります。
当記事で紹介したリスク管理については、TCGのみならず様々なことに活用できますので、ぜひTCG以外にも活用してみてはいかがでしょうか。