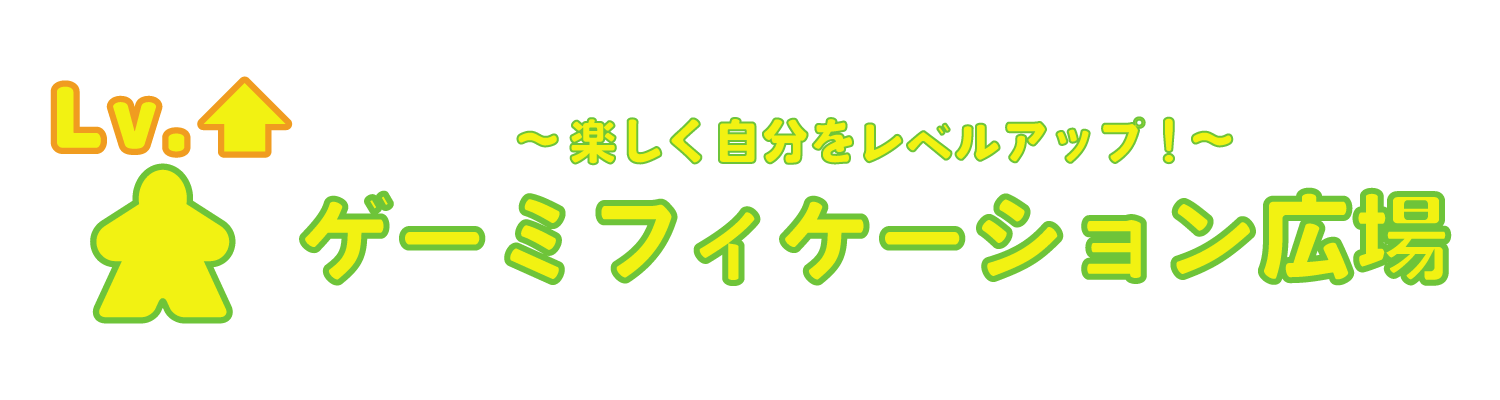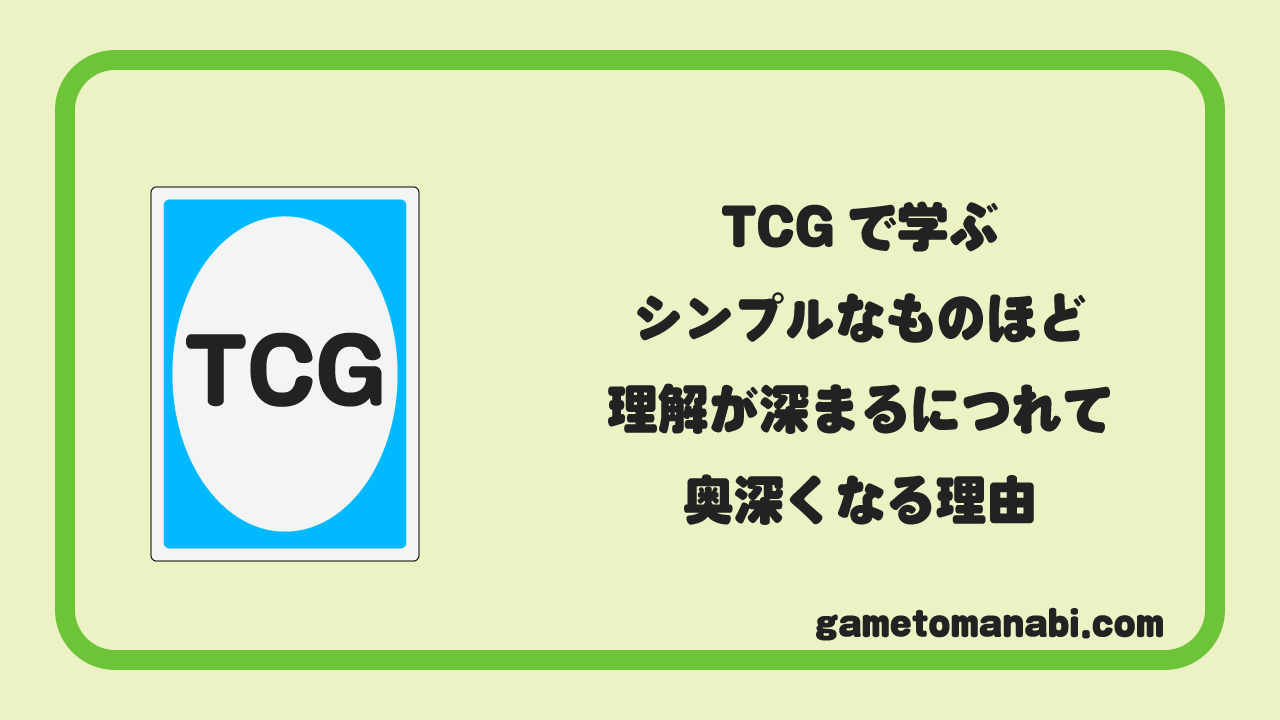- シンプルなデッキと複雑なデッキ、極めるならどちらが良いかを知りたい
- シンプルなものほど理解が深まるにつれて奥深くなる理由を知りたい
当記事では、シンプルなものほど理解が深まるにつれて奥深くなる理由を、TCGに例えて解説していきます。
当記事を読むことで、シンプルなものほど理解が深まるにつれて奥深くなる理由が分かり、現状の把握に役立つでしょう。
複雑なデッキとシンプルなデッキの違い
TCGのデッキは、大きく分けて
- カードの種類が少ないシンプルなデッキ
- カードの種類が多い複雑なデッキ
の2つに分かれます。
カードの種類が少ないシンプルなデッキは、最初は簡単
カードの種類が少ないシンプルなデッキは、カードの種類が少ないため再現性が高く、基本の動きを覚えやすいという特徴があります。
しかし、カードの種類が少ないということは、カード1枚ごとが持つ役割が多いということでもあります。
例えば『A』2枚『B』1枚が必要な場面で『A』『A』『A』『B』『B』の5枚から3枚選ぶ場合、『A』3枚、『A』2枚『B』1枚、『A』1枚『B』2枚の3つの選択肢から『A』2枚『B』1枚を選ぶ必要があります。
そして、実際の試合では全く同じ場面に遭遇する回数は非常に少ないため
- 『一』に対応→『A』2枚
- 『二』に対応→『A』1枚
- 『三』に対応→『A』1枚『B』1枚
- 『四』に対応→『B』2枚
- 『五』に対応→『B』1枚
場面1=『一』+『二』なので、『A』3枚を選ぶ。
場面2=『三』+『五』なので、『A』1枚『B』2枚を選ぶ。
のように基本的なパターンを応用する力が求められます。
シンプルなものほど理解が深まるにつれて奥深くなる理由
シンプルなものほど理解が深まるにつれて奥深くなる理由は、この応用パターンの見える範囲が理解が深まるにつれて広がってくるからです。
上級者によるシンプルなデッキの解説が長文なのは、この見えている選択肢の多さが理由です。
上記の例であれば、『一』『二』『三』への対応の仕方しか知らない場合は
- 『A』3枚
- 『A』2枚『B』1枚
の2択ですが、『一』『二』『三』に加えて『四』『五』への対応の仕方も知っている場合は
- 『A』3枚
- 『A』2枚『B』1枚
- 『A』1枚『B』2枚
の3択になります。
そのため、シンプルなデッキは、知識量が増えるほど試合中の選択肢が増えていきます。
カードの種類が多い複雑なデッキは、最初が難しい
カードの種類が多い複雑なデッキは、カード1枚ごとに専門的な役割を持たせているので、カードごとの役割を覚えないとまともに使いこなすことができません。
しかし、カードごとの役割さえを覚えてしまえば、必要な場面が分かるため選択肢を減らすことができます。
例えば『A』が必要な場面で『A』『B』『C』の3枚から1枚選ぶ場合、選択肢は3つありますが、『A』が必要な場面を理解していれば『A』1択にすることができます。
また、妨害などで『A』が使えない場合でも、『A』を使うための方法を考えるだけで良くなります。
つまり、カードの種類が多い複雑なデッキは、シンプルなデッキとは逆に知識量が増えるほど試合中の選択肢が減っていきます。
極める難易度はシンプルなデッキも複雑なデッキも変わらない
シンプルなデッキも、知識量が増えてくると選択肢が増えるため、複雑なデッキと同じくパターンで役割を覚えて、不要な選択肢を減らしていく必要があります。
そのため、極めるのであればシンプルなデッキも複雑なデッキも難易度は変わりません。
まとめ
- カードの種類が少ないシンプルなデッキは、最初は簡単だが、知識量が増えるほど試合中の選択肢が増える
- カードの種類が多い複雑なデッキは、最初が難しいが、知識量が増えるほど試合中の選択肢が減る
- 極めるのであればシンプルなデッキも複雑なデッキも難易度は変わらない
シンプルなものほど、理解が深まるにつれて見える範囲が広がり、奥深くなります。
この見える範囲を広げることで、更に成長していけるでしょう。